今でも忘れられない1つの記憶がある。
記憶の中の俺はまだ小学生で図工の授業を受けていた。
図工室の隣の席には1人の女子がいる。
手には白い紙粘土、彼女はそれを小さくちぎっては丸めたり
延ばしたりしていた。
みるみるうちに始めはただの塊だった粘土には命が吹き込まれ、
粘土板の上は熊やウサギなどの動物や皿や湯のみなどの日用品を
かたどったごくごく小さな造形物で埋められていく。
そして俺はまるで魔法のようにそれらを生み出す手先にずっと
見とれているのだった。
隣に座っていた相手の名も顔も覚えておらぬのに、その光景は
何年も経った今でも俺の中から消え去ることはなかった。
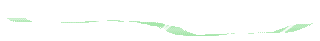
魔法の手
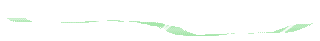
それはいつものように練習を終わらせて、テニス部の仲間達と
下校している最中のことだった。
メンバーは俺と柳蓮二とジャッカル桑原、それに後輩である切原赤也だ。
部活の後は大抵この4人ですっかりと日の暮れた道を歩いている。
喋りながら歩くのは言うまでもないが主に話すのは赤也とジャッカルで
俺と蓮二は後ろから静かにその様子を眺めていることが多い。
この日もそうだった。例によって赤也とジャッカルが他愛もない話で盛り上がり、
俺と蓮二はそんな彼らを見つめながらも、彼らの話とは
関係ないことを2人で話す。だが、この日は思わぬことがあった。
「あ、そーだ、ジャッカル先輩。」
いつものようにせわしなく話し続けていた赤也がふいに手をポンと叩いた。
「例の人どーなんスか。先輩のクラス、今日美術あったんでしょ。」
「ああ、あいつか。まただ、また。」
「うっわ、学習能力なさすぎ。」
「どうせいつものことだけどな。」
「ますます突っ込みどころがあるっスね。」
「何だ、何の話だ。」
俺は思わず尋ねた。
ジャッカルと赤也がこちらの要領を得ない話を始める
―それも比較的盛り上がっている―のはいつものことだ。
俺とていちいち干渉したりする訳ではない。
しかし今日に限っては、赤也が妙に意味ありげな表情で
物を言っているのが何となくひっかかった。
俺が口を挟んだ途端、赤也が妙にニヤニヤした。
多分俺が珍しく興味を示したことが面白いのだろう、ジャッカルを
軽く肘で突いて説明するよう促す。
わざわざ他人に任せず自分でやればよいものを、
こいつには本当に困ったものだ。
自らも困ったようにため息をつくジャッカルの話はこうだった。
奴のクラスにはという女子がいる。
特に優秀でもなければどうしようもないうつけ者でもなく、
普段は人の話題に上る類の人物ではないという。
そんな女子と赤也の言っていた美術の授業がどう関係するのか
俺は初め解せなかった、が、ジャッカルの話を聞いてすぐに得心がいった。
は美術の授業で時間内に作品を仕上げた例がなく、
しばしば居残りをしていることでクラスでは評判らしい。
「随分と変わった奴だな。」
俺が感想を漏らすとジャッカルは、だろ、と呟く。
「あいつ作りこみすぎなんだよ。今日だって土台の入れ物は
とっくに出来てるってのにゴチャゴチャ細かい飾りを作りにかかって。
何か昔っから粘土触ったら見境がねぇ奴だったらしいけどな。」
粘土、という言葉に反応して俺の脳裏に未だに消えぬあの記憶が蘇る。
図工室で俺の隣に座って一心に何かを作り続ける少女、
しかし何度思い返しても思い出せるのは粘土を弄っている
その手先だけでその顔も声も思い出すことは出来ない。
おそらくあまり親しくなかったせいなのだろうが。
「それはそれでよかろう。」
そう口にした途端、一同の目が一斉に俺に注いだ。
「珍しいこともあるものだな、弦一郎。」
赤也とジャッカルの2人と途中で別れた後、蓮二が言った。
「何だ急に。」
怪訝な顔で問えば、蓮二は小さく笑う。
「いや、お前が赤也達の話に首を突っ込んだのがな。」
言われても無理はない、と思う。現に俺自身が何故わざわざあいつらの話に
干渉してしまったのか自分でわかっていない。
「まさか、とは思うが、例の彼女のことでも思い出したか。」
言われて、俺は腹の底でギクリとなった。
元々ごまかしているつもりもないが、俺とて人の子だ、
言い当てられるとどうにも居心地が悪い。
「気持ちはわからないでもないが、果たしてが
お前の記憶の人物と一致するかどうかは何とも言えないな。」
「蓮二、お前はを知っているのか。」
「ああ、一応は。」
蓮二は言った。
「知ってる奴は知っている。」
「どういった人物だ。」
蓮二の笑みが深くなった。どうやら彼も俺がに興味を持ったことを
面白がっているらしい。
「ジャッカルも言っていた通り、特に人目を引くタイプじゃない。
が、何故か一度関わると忘れがたい所がある。
俺はなかなか面白い奴だと思うが、お前がどう思うかは保証しないよ。」
そんなことを言われると非常に不安になるのだが、
その一方でどこか気になっている自分がいた。
とは言うものの、自分の為すべきことに追われていると
そんなことなど忘却の彼方へと消えていく。
2日3日も過ぎれば、のことなど考えている余裕はどこにもなかった。
誰だって目の前にやることがあるのならば、
顔も知らぬ人物に思いを馳せることなどないだろう。
故に俺は全国制覇の為にテニスの練習に
打ち込むばかりの毎日を送っていた。
が、一方で消えることのないあの記憶は隙を見ては
俺の中に蘇ってきて、一瞬俺に自分の無骨な手に目を落とすという
余計なことをさせる。面倒な話だった。
この大事な時期にそんなことを思い出してどうするというのだ。
それにそんなことを思い出して俺は一体どうしたいのだ。
自分の行動に戸惑いを覚えながら練習を再開することもしばしばだった。
おそらく自分では気がつかなくとも第三者の目には
何か目立つものがあったのだろう、
とある日の朝練の時、蓮二がどうかしたのかと尋ねてきた。
俺は一言、問題ない、と答えたが蓮二は納得した様子がない。
「またあのことでも考えていたのか。」
笑いながら言う蓮二に俺はむっとした顔をするしかなかった。
美術の授業があったのはそんな日の6時間目だった。
何の因果か扱うのは粘土、それも課題は自由と来ている。
クラスの連中がどうしようかとザワザワする中、
俺も粘土を手にとってみる。さて、何を作ったものか。
自由課題というのは時によっては厄介だ。
特に俺の場合、こういうことにはとことん疎い。
長く考えた挙句、俺は近所にいる犬を象ってみることにした。
土の塊をこねて犬の姿を形にしていく。耳、目の形、毛並みなど
全てを頭に浮かべながら。
そうして思考に時間がかかった割に、俺の作品は授業時間内に出来上がる。
出来上がった自分の作品に対して俺は正直どうということはないな、
という感想しかなかった。
当然、これも勉学の一つなのだから不真面目にはしていない。
だがテニスをしている時と比べるとあまりに俺の内面は冷めていた。
美術教師は俺の作品を見て、よく出来ている、さすが真田だと口にした。
周囲もやたら褒めそやすか、あるいは嫉妬の視線を投げかけてくる。
だが一方の俺は満足していなかった。
違う、違う。頭の中でそう繰り返す。
しかしそれが何と比べての『違う』なのか、初めはわからなかった。
しばらく自分の作ったものを見つめているうちに比較の対象が思い浮かぶ。
あの時、隣りに座っていた少女だ。
そうだ。俺の作った物など、彼女の足元にも及ばない。
確かに俺の作ったそれは所謂リアルな形はしていた。
(自分で公言するのも憚られるが)
大抵の人間なら小学生の作るものより俺の方がいい、
と言うに決まっているだろう。
しかし、俺からすれば形は似ていても何かがおかしい。
あの少女の作ったものは何もおかしくなかったのに、俺のはおかしい。
何がと聞かれても答える事は出来ないが、
その何かが足りないせいで、俺の造形物はどれだけ外が
真に迫っていようとも似て非なるものでしかない。
周囲がこちらに注目する中、俺はそれがまるで
別世界のものであるかのようにまるっきり気に留めていなかった。
それからまた数日が過ぎた。
俺はその時、職員室での用事を済ませて自分の教室に
戻ろうとしているところだった。
放課後だったが、今日は部活がない。
試験期間が近づいていたからだ。
早く教室に戻って帰り支度をしよう。
そう思っていた時、丁度ジャッカルのクラスの教室の前を通りかかった。
廊下側の窓が開けっ放しになっている。
ほとんど人のいないこの時間に何と無用心なと思って、
俺は窓を覗き込んだ。
誰もおらぬなら、俺が閉めていくとしよう。
が、誰もいないと思われた教室には人の気配があった。
そして、そこには1人の女子生徒がいる。
だった。
顔も知らぬのにすぐそれ、とわかったのは彼女が机の上に
粘土板を置いているのが窓からでもわかったからだ。
ジャッカルの所属するクラスの教室でこのような行為をする女子はそうおるまい。
ついうっかりと凝視していたら、とうとう本人がこちらを見た。
廊下の窓から覗き込んでいる珍客が気になるのだろう、
不思議そうに首を傾げる。
が、すぐに自分の手元に視線を戻した。まるでまるっきり興味がないかのように。
それでも見つめる俺がさすがに気になったのか、もう一度こちらを見た。
「どうかした?」
発せられた声は静かな教室に妙に響き渡っていて、
俺の動揺を誘うには十分だった。
それでも、
「か。」
いちいち相手に確認を取っている自分がわからなかった。
そして、それに対する相手の返事は
「何でそんなくだんないこと知ってるの。」
だった。
次の瞬間、俺は教室に入っての隣の席に座り込んでいた。
「へー、じゃあお宅、桑原と同じテニス部なんだ。」
「うむ。お前はジャッカルとは親しいのか。」
「喋ったこともないな。向こうから近づいてきたことないし、
こっちだっていちいち用はないし。」
「そ、そうか。」
独特の言い回しはおそらく俺でなくとも彼女と深い関わりの無い者には
返事がしづらい。
一見、ひどく皮肉に聞こえるのだ。
相手によったらが不機嫌だと勘違いするところだろう。
よく見たら、不機嫌な雰囲気を漂わせている様子が一つもないのだが。
「部活は。」
「この状況見て、入ってるよーに見えるかね。」
「確かにそうだが。」
俺はここで一呼吸置いた。特に人見知りでもないのに妙に消耗した気分だ。
蓮二は以前は面白い人物だと言っていただろうか。
正直、俺には面白いと思うことが出来なかった。
確かに黙っていれば普通の奴だ、しかしこの特有のひがんだような口調には
戸惑ってしまう上、ともすれば不快感も伴う。
一体こいつのどこが面白い、と言えるのだろうか。
そんなことを考えていれば、必然沈黙が訪れる。
ふと気がつけば、は俺の存在など完全に忘れてしまったかのように
ゴソゴソと何かをやり始めていた。
その手元にはプラスチックの蓋がついた粘土の入れ物がおいてある。
子供用に販売されている色つきの粘土だ。
は丁度その蓋を開けているところだった。
そういった類の粘土はどぎつい原色の赤や青のものばかりだと思っていたが、
が蓋を開けた中身はそうではない。淡い水色や桃色、黄色など世間では
パステルカラーとでも言うだろう色彩ばかりだ。
「今近所のスーパーが改装するからって在庫一掃セールやっててさ、」
入れ物から薄桃色の粘土を選んで指先で少し取り、
こねながらは突然言った。
「丁度文房具売り場に行ったらこれがメチャクチャ安くなってたんだ。」
これだと色をつける手間も省けるしね、と彼女は笑う。
そんな彼女に俺は、そうか、としか答えられなかったが
の笑った顔は先程までの皮肉めいた物言いとは
全くかけ離れた屈託の無いものであることに気がついた。
なるほど。蓮二が面白い、と言っていたのはこういうことか。
その間にもみるみるうちにがこねていた薄桃色の小さな塊が丸みを帯びてくる。
ある程度球形に近づいたところではそれを少し潰し、手元にあった棒
(よくみれば使わなくなったボールペンの軸だった)で薄く延ばし始めた。
「あ、いけない。」
桃色の粘土を適当に延ばしたところで、はボソリと呟いて
今度は白い粘土を取り出すと同じような作業をする。
最終的には、薄く延ばした白い粘土が2枚、桃色のが1枚出来上がる。
ここから何が出来上がるのか、俺にはとんと見当がつかぬ。
ただ、その過程を見つめているだけだ、まるで魔法にかけられたかのように。
どれくらいたった頃だろうか。
「出来た!」
が声をあげる。
「ねぇ、見て見て。」
まるで子供のように目を輝かせて、は自分の手のひらに
乗せたものを俺に見せてきた。
「ケーキ。」
見ればわかった。
「どうよ。」
「なかなか、よく出来ていると思うが。」
「ホント?やったぁ。」
非常に満足そうに呟くと、は次の作業にとりかかった。
俺の手のひらには、白と桃色の断面がうまい具合に
表現されたケーキの一切れの小型模型が残された。
それからもは作り続けた。
水色の粘土からは小さな鼠や魚が生まれた。
薄緑色の粘土は白い粘土と組み合わされ、
ヘラで切り込みを入れられた瞬間にキャベツに変化した。
薄桃色の粘土は今度は愛らしい紅茶ポットに姿を変える。
そして粘土板の上がどんどんそれらの造形物で埋まっていく。
ああ、あの時と同じだな。
ぼんやりと俺は思った。
あの時と違うのは、俺がずっと歳をとったことと、ここが図工室ではないことと、
相手が同じクラスではないことか。
そういえば、知りたいことがあった。
「お前はいつも何を考えてこういうものを作っているのだ。」
俺は尋ねた。何の脈絡も無い問い、普通なら俺がこんな問いを
すれば相手はさぞかし俺に何かあったのかと考えることだろう。
実際、も一瞬驚いたような顔をする。
が、彼女の場合、それはすぐに消えて普通の表情に戻った。
「あんまり何も考えてないなー。いや、考えてないってより
こんなの作りたいってことしか頭になくてさ。
何ちゅうか実物はともかく自分はこういう風にしたい、とか
こんなのがあったらいいな、とかそんな感じだね。」
ここではそんなもんじゃないの、とごく当たり前のように言う。
「例えばさ、自分の持ってないようなの作ってみるの。
可愛いコーヒー茶碗とか、ぬいぐるみとか。
楽しいよ、ホントには使えないけど自分で作った
自分だけのものってのが何かいい感じ。」
それでやっとわかった。俺の作る造形物には想いが籠もっていないのだ。
にしろ、記憶の少女にしろ自分の造形物を象る時、
いつも大事そうに作っていた。
例えそれが人形遊びにしか役に立たないようなごくごく小さなものでも、
例えそれが所謂リアルな作りでなくとも、
彼女は(あるいは彼女らは)こんな風にしたいのだという想いを籠めて
一つ一つを作り上げていく。
そうして想いを込められた土の塊はやがて誰にとっても日常的な、
しかし(陳腐な言葉だが)夢のある何かに形を変えていくのだ。
「真田、大丈夫か。」
が俺の顔を覗き込んでいたのにはっとして、
俺は自分がいつの間にか一人の世界に嵌りこんでいたのに気がついた。
「どしたの、急にどっかへ飛んでったみたいな顔して。」
「問題ない。」
俺は答えた。
「くだらないことを考えていただけだ。」
はああ、そう、とだけ言った。
「しかし、何か妙だね。」
「何がだ。」
「天下の真田弦一郎がさ、帰りもせずにこんなトコで
私のしてること見てるってのが。」
言われてドキリとする。
「何でなの。」
俺は逡巡した。果たして、話してもよいものだろうか。
は笑わずに聞いてくれるものだろうか。
「いや、別にやだってんなら無理に聞くつもりないんだけどね。」
慌てるの気遣いは俺の緊張を和らげた。
そうして俺はポツリ、ポツリと話し始めた、消えることの無いあの記憶の話を。
「へぇ、そんなことがあったんだ。」
俺の話を静かに聞いていたは笑うこともなく、だからと言って
妙に深刻に捕らえることもなく、ただそう言った。
やはりこいつは面白い奴だ。
その辺の中学生ならこんな話をした所で馬鹿にして一蹴することだろう。
「結局その子のことは。」
「今でも思い出せん。小学校の卒業アルバムも見てみたが、
これだ、と思い当たる者がいなかった。
もしかしたら卒業するずっと前にどこかへ転校したのかもしれんな。」
「とりあえずそれと私とが何で関係するんかよくわかんないけど。」
「柄にも無い話だが、懐かしかったのかもしれぬな。
いつもそういったことになるべくかかずらないようにしているつもりだが。」
「いや、そりゃ無理な相談でしょ。」
は言った。
「やっぱ人間なんだしさ。いいんじゃないの、そういうの。」
「そう思うか。」
「うん。」
それからは、さて、そろそろ片付けないと、呟くと机の上を片しにかかる。
特に手伝うことの無い俺は粘土板の上に並ぶ小さな造形物を
眺めていたが、ふと、とあるものに目を留める。
淡い黄色の体に薄茶色の縞がつけられた極々小さな猫、
ゴマ粒のような水色の目がついている。
何故それに惹かれたのかはわからない。
もしかしたら、その猫の目がどこかに似ていたからかもしれぬ。
「、」
「なぁに。」
「よかったらそれを俺にくれぬか。」
「いいけど、どして。」
俺の言葉には訝しげに首を傾げる。
自分でも突発的な発言に、俺自身も口篭り何か言わねばと
しばし考えをめぐらせる。やがて俺はこう口走った。
「実は今日は俺の誕生日でな…」
今まで一度も口にしたことがない大嘘だった。
俺の誕生日などとっくに過ぎている。
故に言ってからしまった、と思った。急に気恥ずかしくなって、
俺は慌ててから目を逸らす。
俺としたことが、柄にもなく何をやっているのだろうか。
だがしかし聞かれたからにはその猫の模型を自ら欲した理由を
何でもいいから提示しておくべきだと考えたのだ。
内心取り乱す俺に対し、は納得したようにへぇ、と呟くのみだった。
いや、納得したのではなく単に何も考えておらぬだけなのかもしれない。
という人物は作品を作る時は細部にまでこだわるにも関わらず
他人についてはその限りではない雰囲気がある。
「だったらあげる。」
の手がすっと伸びてきた。そのひらには俺の人差し指の先から
第一関節くらいの小さな小さな猫が乗っている。
「うむ。」
ちゃんと礼をと思っていたがうまく言うことが出来ず、
俺は猫をそっとつまみあげるとそれだけ呟いた。
結局、が俺の記憶の人物と一致するかどうかはわからなかった。
自身が俺を見ても何も言わないし、(もしかしたら言わないだけかもしれぬが)
俺も最早どうでもよくなっていた。
ただ確かなのは、以降俺とは親しくなったということと、
彼女の側にいると心がこれまでになく穏やかになるということだ。
粘土に命を吹き込んでしまうあの魔法の手は、
ひょっとしたら俺を癒すという効果もあるのではないかと、
今でも柄にも無いことを思っている。
終わり
作者の後書(戯言とも言う)
この話は本来、去年真田の誕生日夢にと思って執筆していたものでした。
ところが、例によってトロい私は書いてる最中に
スランプを起こして結局、去年は真田の誕生日(5月21日)に
間に合わせることが出来なかったんです。
しゃあない来年に回すか、と思ってたんですが
今年は仕事やなんやの都合で結局放置状態。
一月以上更新してないという現状も重なって、
とうとう今回通常の短編に書き直してのお目見えとなりました。
楽しんでいただければ幸いです。
ちなみに背景画像は例によって自前。
子供の頃猫商人と一緒に作ったものを
わざわざこのために引っ張り出してきました。
確か、海老と帽子は猫商人の作だった気がします。
もっと色々あったはずなんですが発掘できず。残念。
2006/06/25
真田弦一郎夢小説メニューへ戻る。